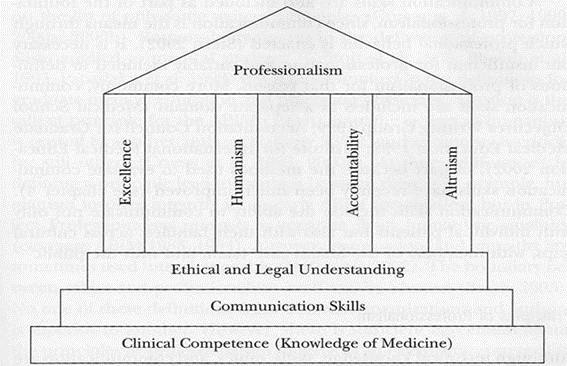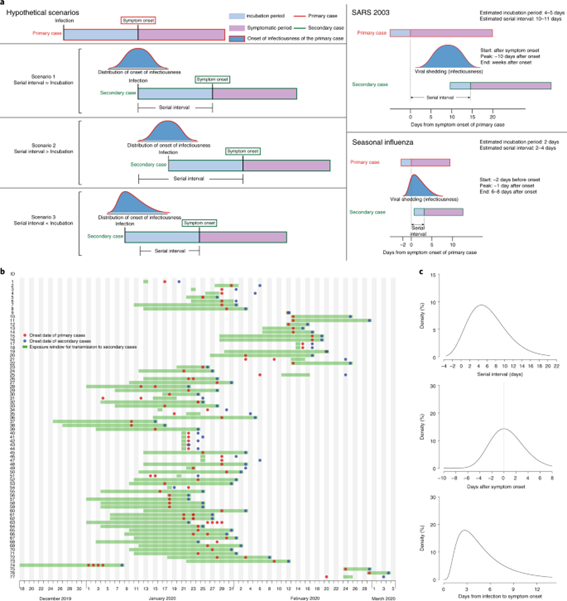 2023.11.23
2023.11.23
本学の建学の精神は、多職種の「優れたQOLサポーター」を育成することにあります。QOLは通学バスの側面にも大きな字で書かれていますので、本学の皆さんには馴染み深い言葉ですが、今回はQOLについて改めて考えてみました。
Lifeには「生活」だけでなく、「生命・命」や「人生・生」という意味もありますから、QOLという言葉にも、普通訳されている「生活の質」にとどまらない拡がりがあります。このようなQOLを、誰がどのようにして測るのでしょう。QOLが高い、低いとはどういうことなのでしょう。
QOLの評価尺度にはまず、一般的な尺度と疾患特異的な症状を評価する尺度があります。複数の次元の質問に答えるプロフィル型の一般的な尺度として、特にEQ-5DやSF-36などがよく用いられています。これは回答者の主観的特性が定量的に数値化されたものですので、ここではこれを「医学的」QOLとしましょう。回答者は、意識があり、自らの状態をよく把握していて、意思伝達が可能な個人であることが前提です。回答者の主観的判断ですから、他者によって判断されたQOLは回答者の主観的特性にはなりません。この立場では、他者による判断は回答者のQOLとして採用できないことになります。さらに、認知症などでこの前提条件を満たすことができない人のQOLについては、自律した個人とは別の議論が必要になることも言うまでもありません。
少し古くなりましたが、New jerseyのJohn Bachによる報告(1993)があります。筋ジストロフィーを主とする、長年人工呼吸器を使用している患者さんたちと、この人たちに日常のケアを提供している各種の専門職の人たちにそれぞれ、Life Satisfaction Index (LSI) という指標を用いて、0から7点満点で現状を評価してもらうと、ともに約5.0点で変わらないという結果になりました。次に、この専門職の人たちに、自らがケアを担当していて、人工呼吸器をつけて生活している人たちに代わって、彼らのLSIを推定してもらうと、平均2.4点と当事者による評価の半分の値になったというのです。他者が当事者に代わってそのQOLを判断することの危うさは、以前から指摘されていたのです。
一方、「医学的」QOLに対して当事者がどのような価値を見出したのか、自らが置かれている医学的な状況にどのような価値があると判断したのかを評価するためには、医学的QOLよりもさらに包括的なQOL尺度が必要になります。当事者によるこのような価値判断が付加されたQOLを、ここでは仮に「個人的」QOLとしましょう。例えば、Schedule for the Evaluation of Individual QOL: a Direct Weighing procedure for QOL(SEIQoL-DW)という評価法が1995年にアイルランドで開発されています。回答者が重視する生活上のさまざまなドメインを回答者が選び、自ら重み付けをして集計する方法で、選ばれるドメインは経時的に変化していきますが、評価を続けることができます。国立病院機構新潟病院の中島孝院長らが日本語訳を作成して普及に努めてきましたが、やはり煩雑だからでしょうか、広く利用されているとは言い難いです。
では、「医学的」QOLに基づいて、他者との比較はできるでしょうか。他疾患の患者さんとの比較できるでしょうか。QOLが低いことを「助ける価値がない」という根拠に用いることはできるでしょうか。
医療経済学ではQALY(Quality-Adjusted Life Years)という指標が費用対効用分析に広く用いられていますが、これはQOLと生存年数を掛け合わせた効用値です。ここでのQOLは、完全な健康状態を「1」、死亡を「0」として数値化したもので、これに生存年数を掛けたものを積算してQALY値が算出されます。例えば、QOLが1の健康な状態で10年生きた場合はQALY=10、その後QOL=0.5の状態で10年生きた場合はQALY=5で、合計は15QALYとなります。有益な医療活動ほど、高いQALY値を生み出すとされ、効果的な医療活動とは、1QALY当たりのコストが可能な限り低いものであり、それが優先順位の高い活動とされます。ですから、QOLの評価方法が課題となるのですが、脳卒中後遺症で右半身麻痺と失語を合併している患者さんのQOLはいくつとするのでしょう。左半身麻痺のみだったら値は変わりますか。こうした患者さんを身近に診てきた医師としては、QOLとしては上述した「個人的」QOLを用いるのが望ましく、QALYのような指標をQOLと呼ぶこと自体に違和感を覚えます。
医療経済学ではQALYを導入することによって、医療の費用対効用を評価することができるようになったので、QALYの評価は既に定まっていると思いますが、さまざまな批判もあります。そもそも「完全な健康状態」が最高なのでしょうか。完全にdisease-freeである状態を健康とするのは、未だWHOの定義にもありますが、今や古い健康観というべきではないでしょうか。超高齢で、完治はし得ない複数の疾病をかかえながら生活して行かざるを得ないわが国のような社会では、健康とは「完全に疾病がない状態」とはもはや言えないでしょう。複数の疾病を抱えながらも、それをやり繰りし、レジリエンスを発揮しながら、「QOL」を高めていけることを健康な状態と考えるパラダイムシフトが必要と思います。
満足とは程遠い状態で長く生きるよりも、期間は短くても「健康な」状態を皆が選択するであろうという考えは、これからの日本社会でも前提にできるのでしょうか。より高いQALYを生み出す医療を高く評価し、1QALY当たりのコストが少ない医療を優先するように、本当に皆が望んでいるのでしょうか。QOLが低く、QALYが低い医療活動は優先順位が低いとすると、QOLが低い患者さんに対する医療は「助ける価値」と結び付いて、価値が低いので不要と判断することになるのでしょうか。功利主義を突き詰めると、「枯れ木に水をやる必要はない」ことになってしまいます。また、QOL評価の前提となる社会保障制度や福祉制度の充実度はQOL評価に影響しますが、このような要素の影響はどう考えるのでしょうか。
QOLを的確な指標によってアセスメントすることは、QOLサポーターとして活動するための第一歩となります。それぞれのクライアントに相応しい評価法を用いればよいのですが、医療経済学上のQALYと、筋萎縮性側索硬化症患者さんの場合のように難病医療の現場で必要な個人的QOLには、乖離があると感じてきました。QOLという用語はやはり本来は、自律した個人の主観的判断に価値判断を加えた「個人的」QOLに対して用いられるべきではないかと考えています。
慶応大学の権丈善一教授は「QALYの倫理的問題はおよそ100年前に言い尽くされている」(「ちょっと気になる政策思想 社会保障とかかわる経済学の系譜」勁草書房、2018年)と書いておられて、専門家には解決済みの問題なのかもしれません。ここでは長年、神経難病や認知症の患者さんと家族を包括的に支える体制づくりに関わってきた一臨床医としての実感を書かせていただきました。本学作業療法学科の能登真一教授はQOL評価の分野で活躍され、新たな指標の提案もなさっておられます。「優れたQOLサポーターの育成」を目標に掲げる本学では、「QOL」という言葉に対する理解を深めていく必要があります。
皆様のご批判、ご教示、ご意見をいただけましたら幸いです。